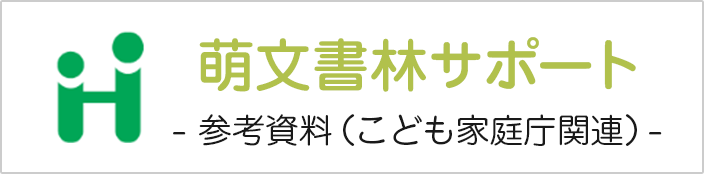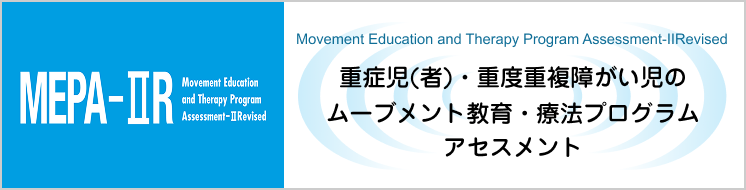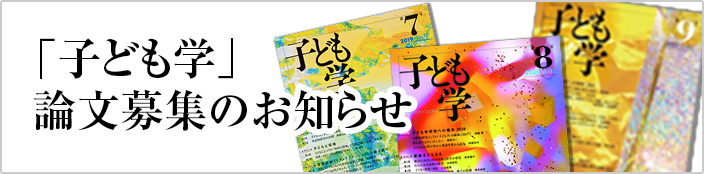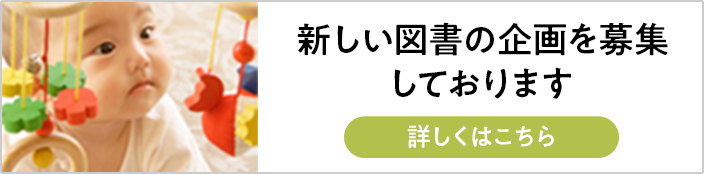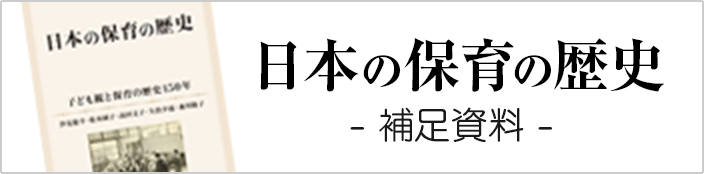レッジョ・インスピレーション ―驚きと発見、対話と思索の教育のために―
- 著者
- 太田素子・小玉亮子 編著 浅井幸子・北田佳子・黒田友紀・小林美帆子・椨瑞希子・藤谷未央 著
- 版型・頁
- B5判カラー口絵付 220頁(2025/08/17)
- ISBN
- 978-4-89347-428-5
- 価格
- 2,860 円(税込)
テキスト採用をご検討の先生方はこちらから見本を取り寄せ頂けます。
概要
「そっくり模倣することをしない」(H. ヨートソン ストックホルム・プロジェクト代表)、レッジョ・インスピレーションとは、どういうことなのだろう
筆者は、日本の保育者がレッジョ・エミリアに深いインスピレーションを受け、それぞれに影響を受け止めているのを目にしながら、その受容の多様さを意識することが必要だと考えてきた。日本人は長い歴史のなかで中国や朝鮮半島の文化、近代に入ってからは欧米文化を速やかに吸収し模倣するなかから新しい様式を生みだすことに長けているといわれてきた。もともと文明は世界各地の相互的な文化伝播のなかで磨かれてゆくもので、模倣そのものが悪いわけではない。しかし模倣するときにそれぞれの文化的な土壌の違いにどれほど意識的であるか、模倣しようとする対象の思想や内容方法、ツールの理解の正確さや深さと、自国の文化理解の深まりは相補的に進むのではないかと思う。
もともと日本のプロジェクト型の教育実践は、20世紀初頭にアメリカや西欧の進歩主義教育から移入されたものだが、その後の発展も含めて現代のプロジェクト型の教育の比較は日本の教育の現状を国際的な視野から振り返る機会ともなる。
スウェーデンの保育は、日本と同様、子どもの遊びや自主的な生活を大事にする伝統をもっている。しかし、そのなかで大きな違いは、いわば非認知的な能力の進展はゆっくりした生活の保障のなかで伸ばしながら、プロジェクトという知性的な活動に教師の助力を集中してゆくところにある。その際、子どもたちの生活のなかから概念の形成や論理的な推理、思索を育てる援助に大人の知的なチャレンジを傾注してゆく。遊びの発展とそのなかでの随伴的な知的発達を尊重する日本の幼児教育の大勢とは異なっている。果たして日本の保育は、レッジョ・インスピレーションを一つの契機として、知性的な保育に変容してゆくだろうか。
(本書「はじめに」を要約)
主要目次
口 絵
第1部 なぜレッジョ・インスピレーションなのか
第1章 スウェーデンのプロジェクト活動 ―いくつかの背景―
1 スウェーデンの保育制度と乳幼児教育への挑戦
2 ストックホルム・プロジェクトとレッジョ・エミリア研究所
3 「テーマ活動」と「プロジェクト」活動
Column1 グニラ・ダールベリ初来日講演 スウェーデンにおけるすべての子どものための包括的で体系的、ホリスティックな幼児教育構築の物語
第2章 さまざまな歴史とさまざまな街 ―世界の幼児教育におけるレッジョ・インスピレーションの可能性―
1 街と歴史
2 異なる歴史、異なる物語
3 特権的な中心と派生的な要素
4 パートナーとインスピレーション
第2部 スウェーデンのプロジェクト
第3章 太陽ミミズと信号鉄ミミズ、“ぐるぐる”と渦 ―ストックホルム市立フォシュコーラのプロジェクト活動―
1 レッジョ・インスピレーションにおける「探求」と「教育ドキュメンテーション」
2 5歳児のプロジェクト「太陽ミミズと信号鉄ミミズ」(2007年)
3 2歳児の探求的保育「“ぐるぐる”と渦」(2008年)
4 2つの教育ドキュメンテーションにみるプロジェクト・アプローチ
Column2 ストックホルム・プロジェクトの回想
第4章 形づくる ―アトリエリスタの役割―
1 カリン・フルネスの経歴と仕事
2 ステーションの形成
3 長期プロジェクトの一例 ─光が叫び、ささやく─
第5章 鹿のプロジェクト ―生と死と再生について―
1 プロジェクトの概要と過程
2 スカルプネック地区の実践と研究 ─インゲラ・エルフストロムとその仲間たち─
3 実践を支える研究組織 ─スカルプネック地区とストックホルムのネットワーク─
第6章 「街」の探求/「森」の探求 ―ソウルバッケン南フォシュコーラの挑戦―
1 ドキュメンテーション『バーガモッセンと世界』を読む
2 プロジェクト「森のなかの友情」から ─プロセスを学ぶ─
第7章 地域社会とレッジョ・インスピレーション ―ステラ・ノヴァのプロジェクトから―
1 ハッロンベリエンという地域
2 ステラ・ノヴァフォシュコーラと多様な家族
3 ステラ・ノヴァフォシュコーラにおける教育実践 ─自然から地域社会へ─
4 学校評価と地域社会
Column3 ヨーテボリ大学のペダゴジスタ養成講座と教師のネットワーク
第3部 レッジョ・インスピレーションの多様性
第8章 イギリスのレッジョ・インスパイアード ―メイドリー保育学校―
1 メイドリー保育学校
2 プロジェクト「蜂の巣マシン」
3 メイドリー校におけるレッジョ・インスパイアードの今日的意義
第9章 カナダ・オンタリオ州のレッジョ・インスピレーション
1 全日制幼稚園とレッジョ・インスピレーション
2 科学的な乳幼児研究と『今日のすべての乳幼児のための学習(ELECT)』
3 全日制幼稚園における『今日のすべての乳幼児のための学習(ELECT)』の機能
4 レッジョのアイデアの導入過程
5 『学習はどのように生起するか(HDLH)』の登場によるペダゴジーの転換
第10章 南オーストラリア州におけるレッジョ・インスピレーション
1 二人の「滞在する思想家」
2 人的投資理論と脳神経科学
3 オーストラリア労働党の教育改革
4 リナルディの滞在とレッジョ・インスピレーション
補 論 政治的実践としての幼児教育 ―1960年代におけるレッジョ・エミリア市立幼児学校・乳児保育所の設立のコンテクストから―
1 なぜ、1960年代か
2 市立幼児学校設立・乳児保育所における市長・議会の役割
3 女性たちの運動
4 市民たちの関与
INDEX
編著者紹介