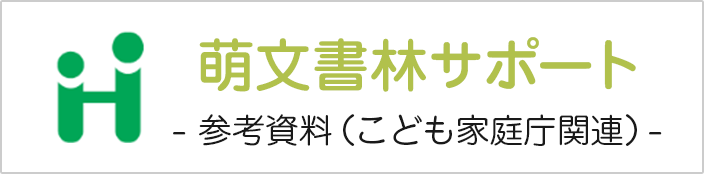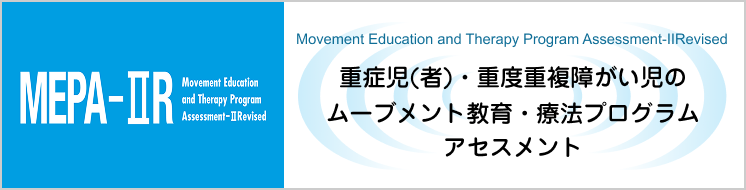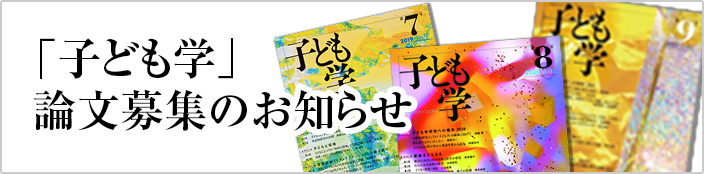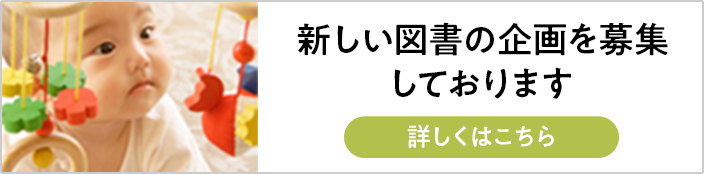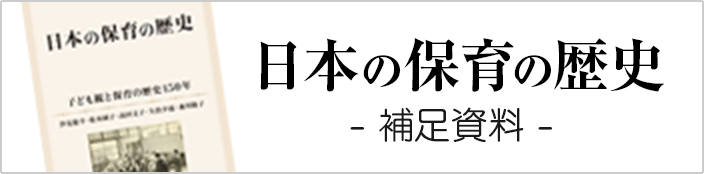環境から考える新しい子ども学 ―DGXで新たな地平をひらく―
- 著者
- 朝岡幸彦・高田文子 編著
- 版型・頁
- A5判 205頁(2025/05/31)
- ISBN
- 978-4-89347-452-0
- 価格
- 2,200 円(税込)
テキスト採用をご検討の先生方はこちらから見本を取り寄せ頂けます。
概要
ポストヒューマニズムという概念をよりどころにし、「DGX」により刷新された子ども学とは。子ども学の刷新と保育実践や教育実践のアップデートを模索する人のためのテキスト。
歴史の進展と時代の変化の中で、ヒューマニズムは今、二つの点でアップデートを迫られています。その一つが、人間と非人間(AIやロボット、デジタル空間、サイバー空間など)との関係です。人間という概念が、人間以外の存在との関係で大きく広がってきており、たとえば、デジタル空間においては実際にそこに人がいなくても、人と人がコミュニケーションを取ることができるという形に変わってきています。会議がリモートで行われることなども、コロナの感染拡大がなければ、ここまで加速度的に変わることもなかったでしょう。まさにこれがDX(デジタルトランスフォーメーション)です。
もう一つが、人間と自然との関係です。20世紀の社会では人間が自然に働きかけて文明をつくってきました。そこには、自然に働きかける主体として人間を特別視する人間中心の見方がありました。それに対して今日では、気候変動や脱炭素化の課題が浮上するなど、自然と人間の関係を問い直すことが重要な課題となっています。人間と自然を対立させるのではなく、人間もまた自然の一部なのだというとらえ方に立って、自然環境と人間との関係をとらえ直していこうという流れが強まっています。これがGX(グリーントランスフォーメーション)です。
DXとGXによる時代の変化を、ヒューマニズムのアップデートを意味するポストヒューマニズムという概念をよりどころとしながら、ポストヒューマンの時代への移行としてとらえたいと考えています。本書では、そうした変化に即応するため、ポストヒューマンの視点からDXとGXを視野に入れたDGXの子ども学を構想しています。
そうした意味で、本書で展開されている環境から考える新しい子ども学は、時代の転換期にあって、子ども学の刷新と保育実践や教育実践のアップデートを模索する人にとって、重要な手がかりを提供するものになることを確信しています。
(本書「はじめに」を要約)
主要目次
巻頭インタビュー 環境から考える新しい子ども学
汐見稔幸氏(聞き手:田中真衣)
序 章 DGX時代の新しい子ども学
COLUMN 自然とデジタルと子ども
第1章 なぜ子どもたちに自然が足りないのか―環境教育・ESD/子ども環境学(1)―
COLUMN 環境問題との出会い―日本人の自然観―
第2章 子どもは環境をどう学ぶのか―子ども環境学(2)―
第3章 子どもにSTEAM教育はどうなされるのか―子どもデジタル論(1)―
第4章 インタープリテーションは子どもたちに何をもたらすのか―インタープリテーション技術―
第5章 子どものためのシティズンシップとは何か―異文化コミュニケーションとシティズンシップ教育―
第6章 ICTは保育と幼児教育をどう変えるのか―子どもデジタル論(2)―
第7章 DGXは地域の福祉をどう変えるのか―コミュニティ調査実習―
COLUMN 保育園から対話の文化をつくる
第8章 子どもにどのような体験が求められているのか―自然体験活動実習―
第9章 みんなで動物園・水族館に行こう―動物園・水族館概論―
COLUMN DXを先取りする天文観測
終 章 DGXは子ども学をどう変えるのか―子ども学の課題と可能性―