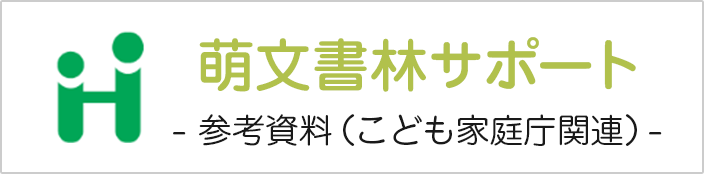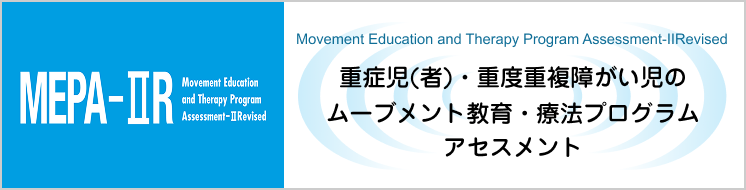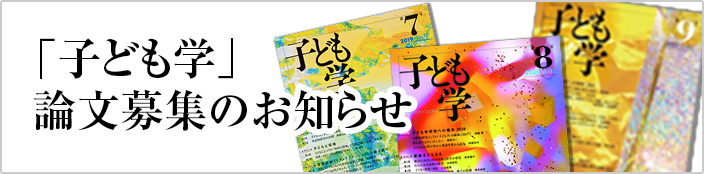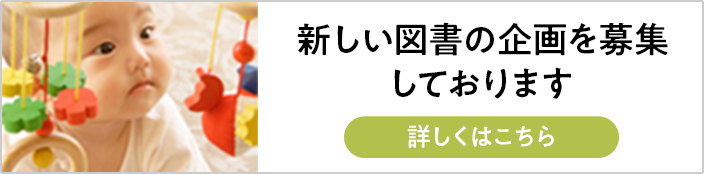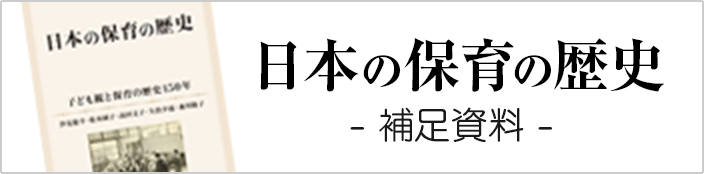初等家庭科教育法 気づく・考える・実践する力を育む授業づくり
- 著者
- 渡瀬典子・倉持清美・萬羽郁子・藤田智子 編著
- 版型・頁
- B5判 220頁(2023/04/28)
- ISBN
- 978-4-89347-400-1
- 価格
- 2,310 円(税込)
テキスト採用をご検討の先生方はこちらから見本を取り寄せ頂けます。
テキスト採用をお考えの先生はこちら概要
「今日の家庭科」を考え、授業づくりを楽しもう。
家庭科教育について探究し続ける実践者・研究者によるテキスト。現代の生活を念頭に、家庭科教育の意義、家庭科の学習活動を通して育つ/育てたい力、学習方法や評価方法などを論じつつ、実践例を丁寧に紹介・解説した。
児童が自ら考え、その考えを伝え合いながら探究していく学習活動のために、これからの教師にはどのような思考や工夫が求められるだろうか。本書に掲載した指導案や授業研究の事例を読み込み、着想を得て、授業づくりに活かしてほしい。
生活の中の問題に気づく力、課題を設定する力、解決に向けて試行錯誤しながら取り組む力を育てるために、教師自身も楽しみながら授業をつくりだすことを願って編まれた一冊。
主要目次
第1章 家庭科を通して「生活」を学ぶ
1 家庭科を通して「 生活」を捉える
2 子どもたちが「生活」について学ぶ意味・意義
3 家庭科教育の特徴と独自性
4 小学校、中学校、高等学校につながる家庭科
第2章 小学校における教科「家庭」のはじまりと展開
1 小学校における教科「家庭」の源流を探る
2 教科「家庭」の誕生と学習指導要領の変遷
3 2017(平成29)年告示「小学校学習指導要領 家庭編」を読む
第3章 家庭科を通して育成する能力と学習評価
1 現代社会で必要とされる能力と家庭科
2 学習評価とは
3 学習評価の方法
第4章 小学校家庭科の指導計画をつくる
1 カリキュラム構成の考え方
2 小学校家庭科の指導計画
3 題材をつくる
4 問題解決的な学習の題材構成
5 題材の指導計画と評価計画
第5章 小学校家庭科の授業をつくる
1 授業設計の視点と学習指導過程
2 家庭科における学習方法
3 実践的・体験的な学習を促進する学習形態
第6章 学習指導案の作成を通して授業を構想する
1 学習指導案とは何か
2 学習指導案(細案)作成のポイント
3 学習指導案(略案/時案)作成のポイント
第7章 家族・家庭生活の授業づくり―他者への気づきのために
1 家族・家庭生活を学ぶ意義
2 家族・家庭生活における学習内容と系統性
3 家族・家庭生活の学習で子どもにつけたい力
4 題材構成の視点と指導案
第8章 食生活の授業づくり―健康で豊かな未来をつくるために
1 食生活を学ぶ意義
2 食生活における学習内容と系統性
3 食生活の学習で子どもにつけたい力
4 題材構成の視点と指導案
第9章 衣生活の授業づくり―衣服の科学と持続可能な社会
1 衣生活を学ぶ意義
2 衣生活における学習内容と系統性
3 衣生活の学習で子どもにつけたい力
4 題材構成の視点と指導案
第10章 住生活の授業づくり―人と地球にやさしい快適さの追求
1 住生活を学ぶ意義
2 住生活における学習内容と系統性
3 住生活の学習で子どもにつけたい力
4 題材構成の視点と指導案
第11章 消費生活・環境の授業づくり―選ぶ力の育成を軸に
1 消費生活・環境を学ぶ意義
2 消費生活・環境における学習内容と系統性
3 消費生活・環境の学習で子どもにつけたい力
4 題材構成の視点と指導案
第12章 わくわくする教材研究―オリジナル教材の開発
1 教材研究とは
教材研究例
給食食材カードを使って楽しく食育!
家庭科の学びは生活のどこへつながる?
授業をするのが楽しみになるような教材研究をしよう
2 オリジナル教材を開発しよう
第13章 教育実習、授業研究会への参加―学習指導案や授業を吟味する
1 小学校における教育実習
2 授業観察
3 授業観察の記録の取り方
4 授業記録を読み取り授業研究会に参加する
5 学習指導案から自分の授業を振り返る
6 授業をアップデートする
第14章 これからの家庭科―現実社会とつながる学び
1 学習しやすい環境づくり
2 家庭との連携を図る授業づくり
3 地域とつながる授業づくり
4 現実社会とつながる学習を紡ぐ
資料(1)家庭科室の使い方
資料(2)さらに学びたい人のための文献・資料リスト